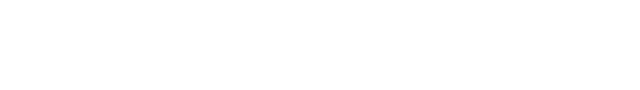医学医療貢献
院長の代表的な医学貢献や医療貢献をご紹介します。
1.狭心症や心筋梗塞
今では一般的におこなわれるようになった、日帰りまたは1泊入院での狭心症や心筋梗塞の既往がある患者さんに対する心臓カテーテル検査治療ですが、数日から1週間程度の入院が一般的であった2002年当時、恩師の御指導のもと、院長が「日帰り冠動脈造影と経皮的冠動脈インターベンションの現状:安全性と有用性」を論文報告しました。我が国で最初の日帰り心臓カテーテルの安全性と有用性を報告した本論文は、日本心血管インターベンション学会の優秀賞を受賞しました。
2.腎動脈閉塞による心不全
繰り返す心不全発作を認める場合に動脈硬化によって腎動脈が閉塞した場合があること、そしてカテーテル治療によって腎動脈閉塞のステント治療を行うことで心不全が改善することを報告しました。心不全発作を認める場合には、心臓だけでなく腎臓にも気を配ることの重要性を示しています。(新聞掲載、ESC Heart Fail. 2015;2:160-63. ESC Heart Fail. 2019;6:319-27. Cardiovasc Interv Ther. 2016;31:171-82. )。
3.下肢閉塞性動脈硬化症
食生活の欧米化と高齢化社会により、下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんが増加していますが、院長が国立循環器病研究センター在籍時に全国の先生方と一緒にJPASSION研究を行い、我が国における下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんの特徴、特に間歇性跛行と重症下肢虚血の臨床的特徴の違いを明らかにしました。
歩行時に足が痛くなる「間歇性跛行」の患者さんは、男性に多く、高血圧、脂質異常症、喫煙歴が多いこと、心臓の冠動脈や頚動脈に狭窄や閉塞が見られやすく、下肢では骨盤内から膝上までの動脈が詰まりやすいことがわかりました。また3年間で約20%の方が心筋梗塞や脳梗塞を発症し命にかかわることがわかりました。
一方、安静時でも足が痛くなり潰瘍や壊疽ができる「重症下肢虚血」の患者さんは比較的女性に多く、脳血管障害や切断既往があり活動度が低下し栄養状態も悪いこと、糖尿病、心不全、心房細動、腎不全の合併が多く、さらに下肢では膝上から膝下足部までの動脈が詰まりやすいこと、傷に細菌感染を伴うことがわかりました。また3年間で約40%と間歇性跛行の2倍の頻度で心筋梗塞や脳梗塞を発症し命にかかわることがわかりました。
4.足の動脈閉塞:Kawarada分類(かわらだ分類)
足の動脈には足背と足底の2つの動脈があります。閉塞性動脈硬化症の患者さんでは閉塞のパターンが3つあることを2012年に報告しました。現在ではKawarada分類(かわらだ分類)として世界中で広く使用されています。
Type1:足背と足底の動脈が開存
Type2A:足背の動脈が開存
Type2B:足底の動脈が開存
Type3:足背と足底の動脈が閉塞
5.糖尿病や腎不全の方の足の毛細血管血流(皮膚灌流圧)
糖尿病や腎不全がある下肢閉塞性動脈硬化症の方では、足の動脈が1本閉塞しても他の動脈から血流が回ってくることで血流が保たれて傷ができにくく、その後に残っていた1本が詰まることで毛細血管の血流不足(皮膚灌流圧が低下)となり傷ができやすくなること、またカテーテル治療で1本でも血流を良くすることで足全体の血流が改善することを報告しました。
6..難病であるバージャー病のカテーテル治療
手足の動脈が詰まる難病であるバージャー病に対して我が国で初めてカテーテル治療の成功を報告しました。現在では世界的にもバージャー病に対するカテーテル治療が行われるようになってきました。(新聞掲載、J Endovasc Ther. 2017;24:504-15. )
7.アジア初の診断治療指針の作成
足に傷がある血管病の患者さんのアジア初の診断治療指針を作成するために院長が国内外の先生方に働きがけ、2018年発表。今では国内外の日常診療で広く使われています。当時の新聞でアジアの先生方との交流が報告されています。
2019年アジア各国(日本、韓国、台湾、香港、シンガポール、インド、マレーシア、タイ、フィリピン)の先生方との国際会議Endovascular Asiaでの記念写真(グランフロント大阪)